哲学者の監査役就任について - 匿名批判者への返信
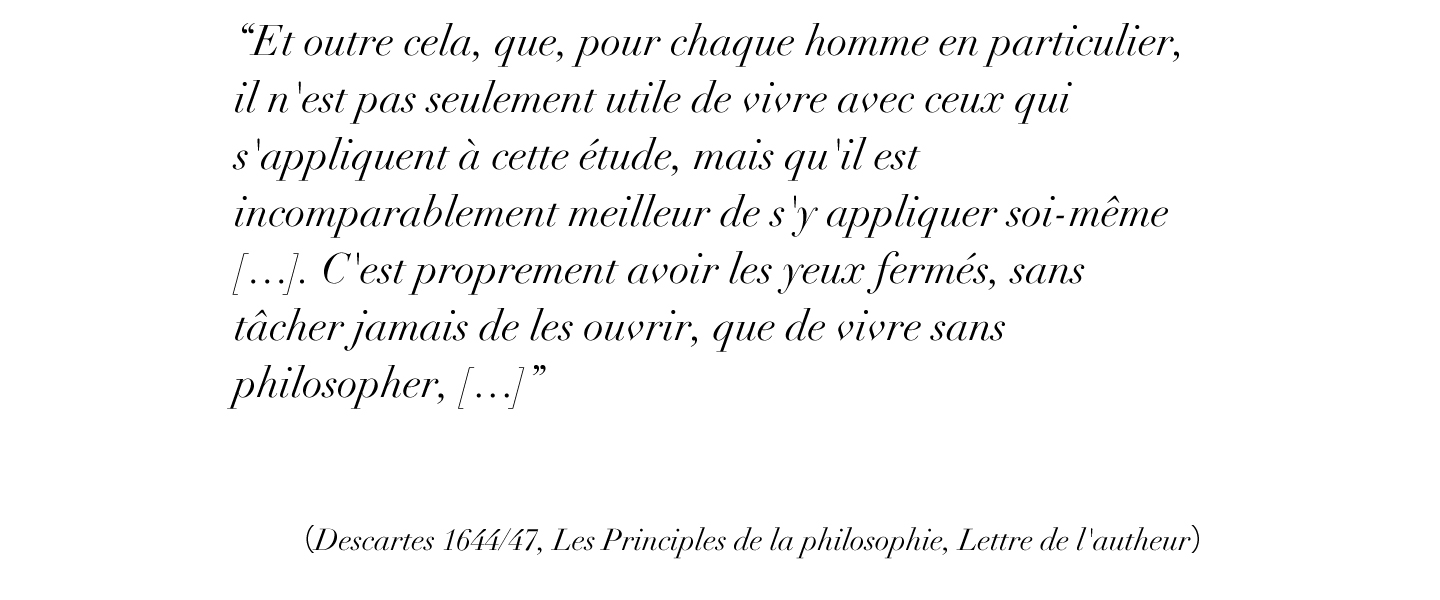
"…個々人についてみても、哲学の研究に専念している人々と一緒に生活するだけでも有益なのですが、しかしそれよりも、自分でも哲学の研究にたずさわってみるならば、それは比較にならないほどよいことであるということ[を私は示そうとしたの]です。(中略)[*1]ところで、哲学することなしに生きるということは、まさしく目を閉じて少しも開こうと努めないことです。"
(デカルト1644/47、『哲学原理』「仏訳者へのデカルトの手紙」)
拝復
頂戴いたしましたご丁寧なお手紙にお返事をしないうちには、私は心を休めることができません。そして、あなたがここで提示なさっておられる二つの問いは、難問であり、たとえ私より学識の深い人物であっても、これを短時日のうちに吟味し、納得のいく回答を与えるのは骨の折れるものとなるでしょう。しかし、私ごときが、たとえ多くの時間を費やしたとしても、余すところのない解決を望むべくもないことは十分に心得ております。したがって、じっくりと時間をかけて考えて、結局のところ代わり映えもしな言葉しかお返事できないというよりは、熱誠が私を動かして書き取らせるがままを、すみやかに紙上にとどめてまいりたいと存じます。
いただいたお手紙の趣では、以下の二点について、私の展望をお知りになりたい御由でございます。すなわち、1.哲学を教え伝えることの可能性、2.哲学の毒としての側面への自覚、です。
まず、第一の点についてお答えするのに、私は名詞としての「哲学」と動詞としての「哲学すること」を区別いたします。前者は今日の講壇において教授されている哲学的学説の体系やその歴史のことを意味しております。後者は、あなたが強調してくださったような、「智を希求する」という態度そのもののことを意味しております。
私の考えるところでは、哲学を教え伝えるということの意味にも、哲学の二義性が反映されるはずです。そして、結論から先に申し上げれば、いずれの場合についても、教え伝えることができるはずだと私は信じております。ただし、その伝え方については繊細な説明が必要となるでしょうから、説明をお待ちください。
まず、名詞としての哲学が、せいぜいのところ哲学の歴史であるとするならば、それを教え伝えることはそう難しいことではございません。というのも、哲学の著作を紐解いていくことで、そこに何が主張されているかについては共有が可能だからです。これはその著作がどれほどに難解であったとしても相違ありません。これに対して、動詞としての哲学することを教え伝えることについてあなたが提示した疑念は、まったくもって正当なものであると私も賛同いたします。哲学し始めるのは個人的な事柄であって、他人に哲学させることはできないのです。この意味で哲学することを伝えることはできません。この動詞形でのあり方が本来の哲学にとって核心的であるとするならば、あなたがおっしゃるように、哲学を教えることなどできないのかもしれません。
しかし、このように考えてみてはどうでしょうか。われわれ人間には等しく哲学の素質があるのだと。ここで私はルソーのように幼児の発達を考えてみたいとおもいます。わたしたち人間は、言葉を操れるようになるとすぐに、万物の名前と区分そしてその理由を知りたいという、強い興味心にかられる動物であるように思われます。この「なぜ」を問う幼子の態度は、万学に通じるような学の基本的な態度ではないでしょうか。そして、根本的な問いへのあくなき探求を進めることこそが哲学の本来の意味、「智を希求すること」なのではないでしょうか。
幼少期には「なぜ」と問うことが許されていたはずです。では、大人になってからはどうでしょうか。おそらく、多くの責任ある主体にとって、「なぜ」という表現は厄介な問いでしかなくなっているのではないでしょうか。というのもそうした主体にとって、まず考えるべきは、なぜその仕事をするかではなく、いかにして職務を遂行するかだからです。私の考える哲学を教え伝えることは、このような大人になった人間に対して、精神の奥底に隠された「なぜ」と問う素朴な力に刺激をあたえること以外ではありません。その具体的な方法の一つが、冒頭の引用でデカルトが述べているように、まずは、哲学をしている人をそうでない人々の只中に置き入れてみることです。大人になった人間は哲学することを忘れているだけなのであり、哲学者の仕方を真似ることで、自らの内在的な能力を発揮することができるでしょう。
第二に、哲学の毒と、哲学者の社会への関わりという点についてお答えします。あなたがお手紙で紹介してくださった事例を聞いて、私はますます心を痛めましたし、私の身の振り方について、真剣に考える必要性を感じました。しかし、まずもって申し上げなければならないのは、私はメタに「哲学者」として介入するつもりはないということです。ご存じの通り、私は長年哲学の研究に取り組んできましたので、哲学的な思考から逃れることはできず、発言にも哲学からの影響がみられるかもしれません。しかし、たとえそうであるとしても、私は自分が哲学に携わる人間であることを、対外的な価値として喧伝したことはないのです。私は、ただあなたの善良にして有能な話し相手でありたいのです。
メタのみなさまに対するあなたの格別の感情には及ぶべくもありませんが、私もメタのみなさんに対する並々ならぬ感情を持っております。私はあなたの幸福を心から祈っているのです。私がメタと関係することにとって、私が哲学者であることは無関係であるとすらいえましょう。もし私が地理学者であったとしても、あなたは私を受入れてくれていたでしょう。ですので、賢明な批判者であるあなたにもう一度お願いします、どうかわたしを企業内哲学者という枠組みで理解しないでください。
とはいえ、私はメタの監査役に就任することになっております、あなたはこの事実に避けがたい自己矛盾を見出したとお考えになるかもしれませんので、私が監査役として何をするつもりなのか、その方向性をお示ししておきます。
私がメタの監査役として取り組みたいのは、みなさんの話を聞くことです。言うまでもありませんが、みなさんは企業に対するコンサルティングを事業として進めてきました。ですので並外れた課題解決能力があります。したがって、私にできることは、せいぜいのところ、あなたの話を聞くことしかないのではないでしょうか。もっとも、ただ話しを聞くといっても、それは決して無力で無責任な選択ではありません。
人との関係性にはやはり「作法」があると思います。そしてあなたが嫌悪する自称企業内哲学者は、この作法を欠いているのだと思います。私が尊敬してやまない熊谷晋一郎氏と綾屋紗月氏は、「つながりの作法」という短い書き物のなかで、この作法を「当事者研究」として解明しています。かいつまんで紹介しますと、彼らは1.話し手自身の主観的な観点(当事者性)と、2.当事者性の感覚を類似する経験をもつ他者との対話において間主観的なものとすることを重視しています。この対話を通じて、話し手は自分の経験を客観視することが可能となり、自分の困りごとを自分で把握することが可能となります。当事者研究の目的は、基本的には自分の困りごとを改善する自助であるといえます。
その前提にあるのは、主観的な世界の見え方を聞き入れる、緩やかな対話の姿勢です。このような対話において、他者の立場から考えることは重要ですが、それ以上に大切なのは、他者を完全に理解することはできないということを、つまり己の無知を知ることです。したがって、安易に話し手の困りごとを「事例」化したり、「問題」として抽出したりするのではなく、その人自身が納得できる理解に至るまで、話し続ける/聞き続ける対話が必要です。すでにあなた方は優れた課題解決の能力をもっているのですから、私が目指すべきは、結論を急がない、気の長い対話相手となることなのです。
この対話において、私が重視したいと考えているもう一つの事例があります。それは、かねてから尊敬する医師、森川すいめい氏が北欧の医療現場から輸入した、「オープンダイアローグ」の手法です。こちらについても、簡単に紹介しますと、何らかの困りごとがある人がいるときに、1.当人だけではなく関係する周囲の人々も対話の場にお招きして、2.困りごとの発生から時間をおかずに対話を行い、3.その困りごとは外側の視線からはどんな風に見えるかを当人に直接説明することで、状況の改善を図っていく対話の作業です。オープンであるといわれる理由は、第一に対話への参加者が当人以外にも開かれているからであり、第二に外側の視線をその場で当人につたえることで秘密をつくらないからです。この態度は、話し手を個別の主体(当事者)とみなすのではなく、むしろ社会的力学において形成されるものとみなす点で、当事者研究とは少し異なっております。
強調すべきことだと思いますが、私が目指すのは対話を通じて他者に深入りすることではございません。むしろ「疎にして多」な協働関係を構築することが目的です。一つずつは細い糸であるとしても、複数の他者との協働関係を張り巡らせることができれば、自分が困りごとを抱えたときには、十分な支えとなるからです。先に言及した熊谷氏は先天性の麻痺の当事者でもありますが、彼が人間の自立とは一人でなんでもできることではなく、むしろ「依存先を増やすこと」なのだという理解に到達したことは、この疎にして多な協働関係の重要性を確認させてくれるように思われます。
これまで述べてきましたように、監査役として私にできることは、メタのみなさんがこれまで培ってきた様々な「力」に対して、ほんの少しの方向性を与えるだけなのです。しかし、これこそが私がしてもよいことであり、することを欲することが許されることだと理解しています。それは、清涼感をえるために、わずかに部屋の窓を開けて自然な風を呼び込むようなことだからです。
あらためて、匿名の手紙を送ってくださって、ありがとうございました。あなたともいつかお話しできることを楽しみにしています。またいつでもお手紙を送ってください。
よき批判者に恵まれた幸運に心からの感謝を
繁田 歩
[*1]中略した部分にはつぎの文章がある。
「ちょうど、自分自身の眼を用いて、自分の行く道をきめ、また自分の眼で色や光の美しさを楽しむことの方が、眼を閉じて他の人の導きに従うことよりも、疑いもなくはるかによいことであるのと同じです。もっとも、眼を閉じて他の人の導きに従うことも、眼を閉じたままで、自分だけで学んでゆかねばならないことよりは、まだましではあります。」なお、原文は次の通り
"comme sans doute il vaut beaucoup mieux se servir de ses propres yeux pour se conduire, et jouir par même moyen de la beauté des couleurs et de la lumière, que non pas de les avoir fermés et suivre la conduite d'un autre ; mais ce dernier est encore meilleur que de les tenir fermés et n'avoir que soi pour se conduire."